

神さまに造られた人は、アダムにより罪を負い(命の繋がり・交わりの断絶)、「命の世界(霊の世界)」から「死の世界(この世)」に堕ちました。
「死の世界(この世)」とは、神さまとの「繋がり・交わり」がない世界であり、神さまの光が届かない闇の世界です。そして、「命の世界(霊の世界)」とは、神さまの命(聖霊)を通し神さまと「繋がり・交わり」が持てる世界であり、そこには天の国から光が差し込む世界です。
「死の世界」に堕ちた人々は、その肉が滅びるとき、神さまを受け入れない(断絶)罪により、神さまの裁きを受け地獄に落とされることになります。そこで御子イエス・キリストは、人々を再び神さまとの繋がりのある世界に導くため、この世(死の世界)に人となって来てくださり、十字架に付くことで人の罪を贖い、「命の世界」に通じる道(十字架)を造ってくださいました。
「…わたしは道であり、真理であり、命である。わたしを通らなければ、だれも父のもとに行くことができない…」
ヨハネによる福音書14章6節「命の世界」に至る道は、十字架を通る(①悔い改め、②福音を信じる、③バプテスマによる告白)ことでしか行くことができません。十字架によって、罪の処分をしなければ、「命の世界」で解放されることはありません。これが、「わたしを通る=十字架」のことです。
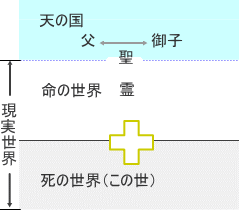
イエス・キリストを自分の「主」と信じる者たち(神の子)は、十字架を通り「命の世界」に入ることができました。そして、今わたしたちクリスチャンは、この「命の世界」にいます。そのわたしたちに神さまは、新約聖書の中で、3つのご命令を出されています。
これら3つのご命令は、「聖霊に満たされ、聖霊によって歩み、互いに愛し合い、全世界に出て行って、まだ救われていない人たちに福音を伝えよ」、となります。そして今回は、第一のご命令「聖霊に満たされて、聖霊(御霊)によって歩きなさい」、ここに焦点をあて進めていきます。
2つの世界
クリスチャンの信仰生活において、「聖霊に満たされ、聖霊によって歩む」ということは、とても大きな意味を持っています。このことをしっかり把握し理解することは、「今後のクリスチャンとしての生き方」、そして「信仰生活を通し、どのような問題が起きてくるのか」、また「成長する上で、すべきことは何なのか」、といことに直結してきます。それは、漠然と「教会に行き、聖書を読み、祈る」という信仰生活から、自分が進むべき道「目標」が定まり、これから先の信仰生活を分かりやすいものへと導くことになります。
【罪と死の世界】
「罪」とは、神さまと人が断絶している状態のことです。神さまと断絶状態にある人は、本来あるべき「神の命」がなく「空」の状態にあります。人は、この「空」を埋めるため、様々なもの(物、金、人など)で満たそうと努力します。しかし、この「空」の場所には、「神の命」しか入ることができません。ですから、いくら人が努力しても満たされることは決してありません。そのことが分からない人は、自らの「飢え」を満たす(空を満たす)ため、この世を「諍い(いさかい)の絶えない世界」にしてしまいます。
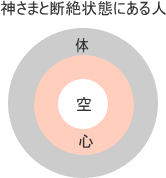
【霊の世界】
「霊の世界に入る」ということは、「空」の場所に「神さまの命(聖霊)を受ける」ということです。つまり、 イエス・キリストを主と信じた者(神の子)は、霊の世界に入り、聖霊が内住(イエス・キリストの内住)されるようになるのです。「あなたがたは神の宮であって、神の御霊が自分のうちに宿っていることを知らないのか。」(Ⅰコリント信徒への手紙3章16節)
そして、「霊の世界」は、天の国からの光が届く世界です。「…神は光であって、神には少しの暗いところもない」(Ⅰヨハネの手紙1章5節)
また、「神さまの命(聖霊)」が内住されることにより、神さまと「繋がり・交わる」ことができるようになります。「すなわち、わたしたちが見たもの、聞いたものを、あなたがたにも告げ知らせる。それは、あなたがたも、わたしたちの交わりにあずかるようになるためである。わたしたちの交わりとは、父ならびに御子イエス・キリストとの交わりのことである」(Ⅰヨハネの手紙1章3節)
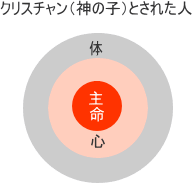
しかし、現実はどうでしょうか。洗礼を受け神さまのいのちを持ちました…さて、その翌日から何か劇的に変わることはあったでしょうか。肉的な考えは一切なくなり、神さまの想いで満たされ、人を愛したくて愛したくて仕方がなくなり、黒かったものが白い物へと変えられ…なんてことは、残念ながらありません。実際は、何も変わっていないことに気付き、「あれ︖何も起こらないけど…」と疑問を抱く人もいるのではないでしょうか。
では、なぜ、わたしたちは「神の子」とされ、「神さまの命(聖霊)」が内住されたにもかかわらず、神さまのご命令である「互いに愛し合い、福音を全世界に伝える」ことが、すぐにできないのでしょうか。実は、ここに明確な原因があるのです。ヨハネは、そのことを「神と交わりをしていると言いながら、もし、やみの中を歩いているなら、わたしたちは偽っているのであって、真理を行っているのではない。 しかし、神が光の中にいますように、わたしたちも光の中を歩くならば、わたしたちは互に交わりをもち、そして、御子イエスの血が、すべての罪からわたしたちをきよめるのである」(Ⅰヨハネの手紙1章6~7節)、と語っています。ヨハネは、「神さまと交わりながら、闇の中にいる」と言っているのです。「神の子」となり「神さまの命(聖霊)」も内住されました。しかし、それ以外のことはどうでしょうか。霊の世界に入り、聖霊さまが飛び交い、天の国から神さまの光も届いているはずなのですが、心も体も以前と全く同じ状態であり、住んでいる場所も以前と変わらず同じ場所です。
ここで、「神さまを信じる」ということを「結婚」にたとえてみましょう。婚約中は、「結婚したら彼女を思い通りにできるな」と思うのですが、いざ結婚してみると、思い通りになるどころか思い通りにされてしまっています。ここに夫婦としての「それぞれの存在をかけた戦い」が起こります。これと同じことが神さまとの関係にもいえます。イエス・キリストを信じたら、「あなたの物は私の物。だから、神さまの力はわたしのもの…」とはなりません。なぜなら、結婚というものは、人格と人格の交わりであり、相手の同意なしに何かをすることはできないからです。神さまと人の関係も同じです。神さまは、神の子とされたわたしたちに、「神さまを主」として生きることを望んでいらっしゃいます。これは第一番目のご命令「聖霊に満たされ、聖霊によって歩む」ということです。しかし、愛のお方である神さまは、人の結婚生活と同様に、相手の同意なく強制的に「ご自分を主」とすることなどおできになれないのです。
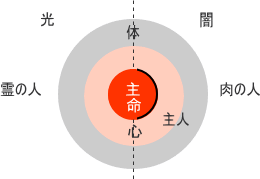
では、人が神さまを「主」とすることに同意したなら、どうでしょうか。神さま(聖霊)は、その人に豊かに働かれるようになり、この世での勝利者(神さまと繋がり、真の意味での自由、幸せを得られる者)としての人生を歩ませられます…。しかし、人にとって、自分以外の者を「主」とし生きていく…この切り替えがなかなかできないのです。なぜなら、人は神さまの命を受けるまで、自分自身を「主人」とし生きてきたからです。つまり、自分自身を「主人」とすることが、止められないのです。
「わたしは、神さまの子供なって、神さまの命を持っているだけで充分です。だって、天国にも行けますし…だから、後は自分の好きなようにさせてください」、と言って壁を造ってしまいます。そうなると、神さまの命(聖霊)は出てこれなくなり、洗礼を受ける前と同じように、自分を「主人」として生きていくわけです。つまり、この人は「神の子」とされてはいるけれども、洗礼を受ける前の自分がそうであったように、自分で自分を救おうとしているのです。人は、これを止めることができません。パウロは、このようなクリスチャンを「肉の人」、そして神さまを主とし、み言葉にそって生きようとするクリスチャンを「霊の人」と表現しています。このことを端的に表現しているのがローマ人への手紙7~8章です。
神さま(聖霊)を阻む自分
パウロは、徹底的に律法に生きた人でした。そして、このパウロは使徒として認められるまで、実に17年の年月を費やしています。彼は、神さまから啓示を受け(異邦人に伝道するため)、家族や先輩使徒たちにも告げす、3年間アラビアで過ごします(ガラテヤ人への手紙1章15~17節)。それから14年かけて、ようやく使徒として認められるようになりました。その時の内面的な苦しみが、ローマ人への手紙7章に書かれています。「私の内側には、物凄く良い神の命が宿っている。しかし、私は神さまの良い想いを実現できない…」、なぜ、神さまの命が宿っているにもかかわらず、自分自身は神の子として生きることができないのか…。パウロは、苦しみます。この間、彼の中では物凄い戦いがあったわけです。つまり、パウロは、クリスチャンになって一朝一夕に聖人になったわけではなかったのです。
彼は救われるまでの長い間、それも普通の人以上に徹底的に律法を守り、生きてきました。それが、神の道と信じて生きてきたのです。「律法を守り、律法に従い」、それで自分が救われると信じて生きてきたパウロでした。このことが、彼の中に神さま(聖霊)が内住された後も、彼自身を苦しめる原因となったのです。彼には、律法を守り自分で自分を救う今までの生き方から、神さまを主とする生き方に、なかなか切り替えができない状態にあったのです。律法に従う自分自身を神さま(聖霊)に明け渡し、神さま(聖霊)に自分が造った壁を打ち破っていただくことが、できないでいたのです。これが彼の苦しみでした。
「そこで、善をしようと欲しているわたしに、悪がはいり込んでいるという法則があるのを見る」(ローマ人の手紙7章21節)。「神さまの命を持ったから良いことをしよう、神さまの想いを果たそうとするけれども、自分の中には悪がいる…」、とパウロは語っています。「もし、欲しないことをしているとすれば、それをしているのは、もはやわたしではなく、わたしの内に宿っている罪である」(ローマ人の手紙7章20節))。ここに書かれている「罪」とは、「自分を主人とし肉によって生きること」であり、救われていない人の「罪」とは、別のものです。自分の中に神さま(聖霊)が住まわれているにもかかわらず、長い間、肉に捉われ自分を主人として生きてきたため、自分で造った「壁」を壊すことができないのです。パウロは、神さまの命を囲むように造ってしまった「壁」のことを「肉の罪」と表現しています。そして、彼はここでの戦いのことを続く22~23節で、「すなわち、わたしは、内なる人としては神の律法を喜んでいるが、わたしの肢体には別の律法があって、わたしの心の法則に対して戦いをいどみ、そして、肢体に存在する罪の法則の中に、わたしをとりこにしているのを見る」と語っています。「内なる人」とは、救われた自分の中に内住されている「神さまの命=聖霊」のことであり、「内に住む聖霊は、神さまご自身が造られた戒めを喜んでいらっしゃる」ということです。パウロは、この「内なる人=聖霊」に従いたいと思う自分と、罪(自分を主人とする)の虜になっている自分との間に「戦い」がある、と述べています。
内住されている「神の命=聖霊」は、パウロに対して豊かに働くために出てこようとしますが、自分を主人とする自分がそれを制止しようと懸命に壁を守りガードします。続いてパウロは、「わたしは、なんというみじめな人間なのだろう。だれが、この死のからだから、わたしを救ってくれるだろうか。 わたしたちの主イエス・キリストによって、神は感謝すべきかな…」(24~25節)と述べています。神さま(聖霊)は私に内住され、善を行わそうとされているにもかかわらず、私はそれを阻止するように懸命にガードしている…わたしは何とみじめな人間なのだろうか…と表現しています。
ここで、神さまの第一のご命令を思い出してください。神さまは、わたしたちに「聖霊に満たされよ」と仰いました。「満たされる」ということは、「支配されよ」ということです。この支配とは、独裁政治における「支配」とは異なり、神さまの「愛のある支配=真の自由」を意味します。「愛」ある正しい関係においては、前述した結婚生活のように、相手の同意のないところに「愛ある支配」は、成立しません。神さまが、その人をどれだけ愛し、大事に大切に思っていたとしても、その人の同意なくしては、その人の人生に介入することさえできないのです。
2つの十字架
では、どうすれば「聖霊に満たされる」ことができるのでしょうか。実は、このことをイエスさまは、福音書の中で何度もわたしたちに語られているのです。イエスさまは、「また自分の十字架をとってわたしに従ってこない者はわたしにふさわしくない。自分の命を得ている者はそれを失い、わたしのために自分の命を失っている者は、それを得るであろう」(マタイによる福音書10章38~39節)と仰っています。
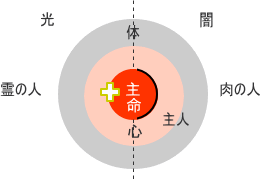
【主の十字架】
イエス・キリストが人の罪を贖うために、ご自身が付かれた十字架。これは唯一の義人である神の御子イエス・キリスト以外負うことが出来ない十字架です。
【自分の十字架(己が十字架)】
「心」と「神の命(聖霊)」が内住されている境にある十字架。これは、自分自身を主人とする「肉の自分」を殺すことができる十字架です。この「殺す」とは、イエスさま(神さま)に「自分にはどうしてもできません」と完全に降伏し、自分を主とすることを止め、イエスさま(神さま)に自分を明け渡す、という意味です。結婚生活にたとえるなら、「体に悪いから、お酒を止めた方が良いわよ」と妻に言われ、「俺も止めたいんだ、でも一人じゃ、どうしたって無理だから、俺が止められるよう助けてくれ︕」と相手に助けを求めると、相手も助けることができます。しかし、「いや、俺はこのままでいいんだ」という人を助けることはできません。つまり、「自分ではどうすることもできない」ということを、まず自分自身が受け止め、謙虚になり相手(イエスさま=神さま)に助けを求め、委ねることです。
人は、イエス・キリストの十字架により罪が贖われ、それを信じる者はクリスチャンとされました。そして救われたクリスチャンは、洗礼を受け「神の命=聖霊」が内住する「聖なる宮」とされました。しかし、多くのクリスチャンが、神さまを「主」とする生き方ができない「罪=クリスチャンの罪」を犯しています。その「罪」を犯し続ける限り、クリスチャンであっても洗礼を受ける前の「肉の人」としての生き方と同じ人生を歩んでいることになります。この「クリスチャンの罪」も、やはりイエス・キリストの十字架につけない限り、赦されることはないのです。つまり、「自分の十字架」とは、自分で自分を赦す十字架ではなく、自分を明け渡す十字架のことです。
マタイによる福音書10章39節の「自分の命を得ている者はそれを失い」の「命」とは、自分を主人としている「肉の自分の命」のことです。また、「わたしのために自分の命を失っている者は、それを得るであろう」の「自分の命を失っている者」とは、「肉の自分に死ぬ者は生きる」ということであり、「それ」は、「神さまの命=聖霊」のことを意味しています。
ヨハネの手紙一1章6~9節
6節の「神と交わりをしている」とは、「救われている」ということであり、「やみの中を歩いている」ということは、「肉の自分として歩んでいるなら」という意味になります。また、やみ=闇とは、音のない世界であり、神さまの声が聞こえない世界のことです。神さまは、闇の中を歩く「クリスチャンの罪」を犯している人に、試練(出来事)を与えられ、闇から出るように働きかけられます。
8節の「罪」とは、「クリスチャンの罪」であり、自分が罪を犯したなら「自分の罪を告白しなさい」と9節に述べられています。「罪の告白」とは、自分を主とすることを止め、自分を明け渡すこと(自分の十字架)です。そして、「わたしたちをきよめて下さる」とは、告白したクリスチャンの罪を「イエス・キリストの十字架」により、きよめられるということです。この過程を経ることで、神さまがわたしたちに求められる「聖霊のみたし=聖別」を得ることができるようになります。
パウロがガラテヤ人への手紙3章で「愚かなるかなガラテヤ人よ…」と怒っていますが、これはクリスチャンでありながら、まだ自分を自分で救おうと懸命に律法を行っている信徒へ向けた言葉です。そこには、行いにより救われるのではないこと、内住している「神の命=聖霊」に自分を明け渡すこと、それにより聖霊がわたしたちを支配できるようになること、そして、そこにこそ真の自由があるのだということ、それらの想いが含まれています。
聖霊に満たされるということは、不思議な現象に自分自身が包まれる、というものではありません。「異言する、預言する、不思議な現象を見るなど」実にさまざまなことがいわれていますが、「聖霊に満たされる」ということは、「聖霊に支配される」ということです。「聖霊に支配される」ための最も根本的な方法は、「神さまの言葉に従おうとすること=み言葉に従おうとすること」です。
わたしたちは、洗礼を受け「神さまの命(聖霊)」が内住されるようになりましたが、わたしたちには依然として古い自分(肉の自分)が残っています。中でも、自分の力で長い間生きてきた人ほど、「聖霊に満たされる」これら一連の過程を経ることは、辛さを伴うことになるかもしれません。そうでなくても、わたしたち大人は、懸命に頭で神さまを「信じよう、信じよう」とするのですから…。しかし、小さい頃から、神さまの中で育てられた子供たちは、違います。「信じる」なんて観念はなく、「愛する」という世界になっています。それは、「どうやったら神さまを愛せるのか」、「どうやったら人を愛せるのか」というものです。どんなクリスチャンにでも、古い肉の自分はあるのですが、長く肉の自分で生きてきた人に比べると、小さくてすむようです。「あなたの若い日に、あなたの造り主を覚えよ…」(コヘレトの言葉12章1節)。でも、80歳の人に比べれば、70歳の人は若いですし、90歳の人に比べれば、80歳の人は若いですから、一時も早く、肉の自分が犯す罪を知り、その罪に太刀打ちできないことを神さま(イエスさま)に告白(降伏)し、助けを求めてください(自分の十字架を負う)。
みことばに従うには
アンドリュー・マーレー師は、「聖霊に満たされる。その為に、あなたたちは色んなことをやっているけれど、聖霊に満たされる一番の近道は、み言葉に従おうとすることだ」と述べています。これは「自分でみことばを守れ」と述べているのではなく、「自分の考えていること」をいつも「イエスの言葉(みことば)」の下に置くようにすることです。イエス・キリストを自分よりも上に置くことです。なぜなら、わたしたちは自分の考えを捨てることはできません。だから、いつでも「み言葉」と「自分の考え」が対立してしまうのです。そして、時には自分の考えが「み言葉」の上にいきそうになる時もあります(肉の自分を優先させる)。その時に、「そうじゃないんだ。自分には、この「み言葉」を守ることはできないけれど、自分の考えの上に置くようにしてみよう」そして「主よ、どうか助けてください。この『み言葉』をわたしが守れますように、この『み言葉』のように生きることができるよう助けてください」と祈るのです。これが「自分の十字架を負う」ということです。そうすると、内なる聖霊が十字架を通り、わたしに働きかけ神さまの想いを実現することができるようになります。自分の力でできないことを、御霊である神さま(聖霊)が助けてくださいます。ですから、聖霊なる神さまは、助け主でもあるのです。この法則をわたしたちがいつもわきまえ、何か出来事が起こるたびに、自分自身の動き「アッ、また自分でガードして、聖霊の働きを邪魔してるな」を認識することです。
しかし、「聖霊のみたし」は、一度できたから一生満たされ続ける…、というものではありません。残念ながら、人は生きている限り、肉の自分となり闇に生きることを繰り返してしまうものです。ですから、自分を十字架に付ける行為は、その都度行わなければいけないことです。そして、何度も自分を十字架に付け「聖霊のみたし」を経験していくと、人には学習能力がありますから、徐々に「ある感覚」が養われてきます。「そうなんだ、ここで自分の考えを通してはいけない」とガードしようとしている自分が分かるようになり、「神さまに委ねよう」と十字架への付け方が分かるようになります。つまり、経験を重ねると、自分が肉で生きようとしていることに一早く気付くようになり、「神さまの命(愛)」に方向転換するようになれるのです。このプロセスが、信仰を成長させ、闇の中(肉の自分)ではなく、光の中を歩める者(霊の自分)とされます。
わたしたちは、洗礼を受け「神さまの命」が内住している限り、天国に行くことはできます。しかし、自分の十字架を経験しない限り、わたしたちはこの地上で「神さまの子供として喜んで、魂の内側から幸せだな」と感じて過ごす(勝利者になる)ことはできません。天国に入ることはできても、この世に負けて生きていく(肉の自分として生きていく)ことになります。イエス・キリストを信じている限り神の子であり、天国には行けます。しかし、肉の自分が強く、壁が厚い(ガードが固い)クリスチャンは、「えっ、クリスチャンをやっていても全然何も変わらないじゃない、むしろ他の人の方が活き活きとしてるじゃない」、と失望感が増し、つまずく人もいます。あるいは、他の宗教の方がよく見え、信仰を変える場合もあります。これは明らかな偶像礼拝であり、イエス・キリストを主とすることを止め、内住している神さまの命を放棄することになりますから、「命のない人」へと戻ることになります。
どんなに惨めな(肉にまみれた)クリスチャン生活であったとしても、「主よ、助けてください」と主を神としている限り、神の子であり天国に行くことはできます。しかし、できるならこのような肉にまみれたクリスチャンではなく、いつでも光の方で生きる霊のクリスチャンとして歩んでほしいと願っています。それには、光の方で生きようとする行為、「教会に行く、集会に出る、み言葉を読む、祈り続ける」これらのことを日々大切に行い、歩んでいかなくてはいけません。「この世=闇」は、クリスチャンをいつも光から呼び戻そうと引っ張っています。ですから、これに負けないように生きていかなくてはいけません。
イエスさまは、わたしたちが「神の子」として生きるため「聖霊に満たされなさい、聖霊によって歩みなさい、聖霊に支配されなさい」と命じられました。これが聖霊のみたし、そして聖別ということです。
![]()